<当サイトではアフィリエイト広告を掲載しております>
はじめに
仕事をしていると、電話の取次ぎや不在連絡を任されることは意外と多いもの。そのときに大活躍するのが「伝言メモ」です。
でも、ただ書けばいいというわけではありません。伝え方ひとつで、「気が利く人」「信頼できる人」と思われることもあれば、逆に「雑な人」とマイナス評価につながることも。
この記事では、できる人が実践している正しい伝言メモの書き方をテンプレート付きで詳しく解説します。新人さんはもちろん、ベテランの方にも役立つ内容です!
ビジネスマナーとしての不在・伝言メモの重要性
伝言メモはビジネスの基本中の基本
仕事をしていると、「○○さん宛に電話が来ました」といった場面に出くわすことが多くあります。そんなときに役立つのが「伝言メモ」です。伝言メモは、その場にいない人へ確実に情報を伝えるための大切な手段です。特にビジネスシーンでは、言った・言わないのトラブルを防ぐためにも、書き残すことがとても大切です。
メールやチャットが主流の現代でも、電話や来客の対応では今なお手書きのメモが活躍しています。たった一枚の紙が、その人の印象を左右することもあるのです。
できる人が書く伝言メモの特徴
「できる人」と思われる伝言メモは、情報が簡潔でわかりやすく、見た目もきれいに整っています。伝えるべき情報が正確に整理されており、読み手がすぐに内容を把握できるのが特徴です。誰が、いつ、何を、どうして、という基本の情報がしっかり書かれているため、後から見直しても「なるほど」と納得できる内容になっています。
このようなメモを書く人は、相手への気遣いができる人だと評価され、自然と信頼が高まります。
社内外の信頼度に直結する
伝言メモは社内だけでなく、外部の人からの連絡を預かる場面でも使われます。たとえば、取引先からの大事な電話を受けた際、その内容を正確にメモできていれば、会社全体の信頼感が高まります。逆に、内容が曖昧だったり抜けていたりすると、相手からの信頼を失う原因になりかねません。
つまり、一枚の伝言メモが会社の印象を左右することすらあるのです。
トラブルを未然に防ぐ効果も
「聞いてない」「そんな話はなかった」というトラブルは、ビジネスの現場ではよくある話です。しかし、正しい伝言メモが残っていれば、こうしたトラブルを事前に防ぐことができます。
証拠として残せるという点でも、口頭よりメモの方が断然信頼されやすいのです。特に、口頭で伝えただけでは忘れてしまったり、解釈のズレが生まれたりすることもあります。書き残すことが最も安全です。
メモ1つで評価が変わることも
同じように伝言を受け取っても、丁寧に分かりやすくメモを書いて渡す人と、殴り書きで雑に書く人では、周囲からの評価が全く違います。日々の小さな行動の積み重ねが「できる人」という印象をつくっていくのです。
特に若手社員や新人は、こうした基本的なスキルがしっかりできることで、信頼を早く得ることができますよ。
「できる人」がやっている伝言メモ5つの基本ルール
誰が誰に向けた伝言かを明確に
伝言メモでは、「誰が」「誰に」伝える内容なのかを明確に書くことが基本です。たとえば「○○株式会社の田中様より、山田課長宛にお電話がありました」といった具合です。宛先がはっきりしないと、メモを受け取った人が自分宛かどうか判断できず、無駄な混乱が生じてしまいます。
複数人で同じ電話を受ける職場では特に、この部分をはっきりさせることが重要です。
日時・名前・連絡先は絶対に記入
電話がかかってきた日時、相手の名前、連絡先(電話番号など)は必ず記入しましょう。これが抜けていると、後で折り返し連絡を取ることができず、大きなトラブルにつながる可能性があります。
伝言を受けたその瞬間に、忘れずに書き込むクセをつけておくことが大切です。特に、同じ名前の人が複数いる場合は、会社名なども一緒に記入すると安心です。
相手の言葉を正確に伝える努力
伝言メモは、「相手の言葉を正確に書き写す」ことが何より大切です。自分なりに要約しようとして内容が変わってしまうと、トラブルのもとになります。わからない部分があれば、しっかりと聞き返して確認しましょう。
「○○についての件で、折り返しお願いします」など、できるだけそのままの言葉を使うようにしましょう。
自分の名前と対応記録も忘れずに
伝言を受けた自分の名前や、メモを渡した時間などの記録も必ず入れましょう。これは万が一、後で確認が必要になったときに、誰が対応したかがすぐにわかるようにするためです。
責任の所在を明確にする意味でも、この一手間はとても重要です。
読みやすさと簡潔さが命
どんなに情報が正確でも、字が汚かったり文章が長すぎたりすると、読み手にとっては大きなストレスになります。伝言メモは「パッと見てわかる」ことが大切なので、読みやすく簡潔に書くことを心がけましょう。
箇条書きや短い文を活用することで、より見やすくなりますよ。
ケース別:好印象を与える伝言メモの書き方テンプレート
上司宛の伝言メモテンプレート
上司への伝言メモは、特に丁寧に書くことが大切です。以下のようなテンプレートを使うと、失礼がなく正確に伝えることができます。
宛先:〇〇課長
日時:10月14日(火)14:35
差出人:株式会社〇〇 田中様(03-1234-5678)
内容:「△△の件で折り返しをお願いしたいとのことです」
受信者:山本(14:36 メモ渡し済み)
上司に対しては、失礼のない言葉遣いと丁寧な表現を心がけましょう。
外部取引先からの電話メモテンプレート
取引先からの電話は、会社の信用にも関わるため、特に正確に記録を残すことが大切です。
宛先:営業部 佐藤様
日時:10月14日(火)15:10
差出人:株式会社〇〇 営業部 山田様(080-xxxx-xxxx)
内容:「見積もりの件で相談したいとのこと。17時までに連絡希望」
受信者:田村(15:11メモ渡し済み)
時間指定がある場合は、特に見逃さないように明記しましょう。
同僚・部下向けのフレンドリーな伝言例
同僚や部下向けには、やわらかく親しみやすい文面でもOKです。ただし、必要な情報はしっかりと書くようにしましょう。
宛先:鈴木さん
日時:10月14日(火)16:00
差出人:○○カフェの担当者(0120-xxxx-xxx)
内容:「予約の件で確認したいことがあるそうです。折り返しお願いします」
受信者:田中
軽い雰囲気でも、ビジネスマナーは忘れずに!
急ぎの要件があるときの書き方例
急ぎの連絡がある場合は、「至急」「急ぎ」などの言葉を大きく目立たせましょう。
🔴【至急!】
宛先:小林課長
日時:10月14日(火)16:45
差出人:〇〇建設 佐々木様(03-xxxx-xxxx)
内容:「明日の打ち合わせ変更について、すぐに確認したいとのこと」
受信者:斉藤
急ぎの内容は、口頭でも併せて伝えるようにするとさらに安心です。
メール・チャットと併用する場合の工夫
最近は、伝言をチャットやメールで伝えることも増えています。手書きメモと併用する場合は、「メールでもお送りしています」などの一言を添えると親切です。
宛先:渡辺部長
日時:10月14日(火)17:00
差出人:〇〇社 林様(080-xxxx-xxxx)
内容:「来週の会議資料について相談あり。詳細はメールでもお送りしています」
受信者:三浦
紙とデジタルの両方で伝えることで、伝達ミスを防げます。
やってはいけないNG伝言メモとは?
情報が足りないメモの実例
伝言メモで最も多いミスの一つが「情報不足」です。たとえば「○○さんから電話あり。折り返してほしい」とだけ書かれていると、どの○○さんなのか、何の用件なのか、いつ電話があったのか分かりません。
相手の名前、連絡先、用件、日時などの必要な情報が1つでも欠けていると、スムーズな対応ができず、相手に迷惑がかかってしまいます。ビジネスでは「相手に手間をかけさせない」ことが基本なので、曖昧なメモは避けましょう。
読みにくい字や略語だらけ
どれだけ丁寧に内容を書いていても、字が読めなければ意味がありません。また、自分だけが分かる略語を使ってしまうと、他の人には伝わらなくなってしまいます。
たとえば「K社 S田サマ 電番 不明」といった書き方はNGです。情報が曖昧で誰を指しているのかも分かりづらく、読み手を混乱させてしまいます。読みやすい字で、略語は極力使わずに記載しましょう。
曖昧な表現や主観が入るケース
「たぶんこういうことだと思います」「怒ってる感じでした」など、自分の主観や予測を含めた内容は書かないようにしましょう。伝言メモは「事実を正確に」伝えるためのものです。推測ではなく、実際に相手が言った言葉をそのままメモすることが大切です。
不明な点がある場合は、「詳細は不明」「内容は聞き取れませんでした」など、分かっていないことも正直に書いたほうが信頼されます。
メモを渡し忘れるミス
せっかく丁寧に伝言メモを書いても、相手に渡し忘れてしまっては意味がありません。特に忙しい職場では、書いたままデスクに置きっぱなしにしてしまうケースも少なくありません。
メモを書いたら「必ず手渡す」もしくは「相手のデスクに見えるように置く」ことを徹底しましょう。チャットやメールと併用して「メモを置きました」と一言連絡するのもおすすめです。
「伝えたつもり」が一番危険
伝言に関して最も危険なのが、「伝えたつもり」になってしまうことです。「メモを渡したつもりだった」「口頭で言ったと思っていた」など、確認せずに安心してしまうのはNGです。
必ず「相手に伝わったか」を確認し、「メモを渡しました」と記録を残しておくことが大切です。自分では伝えたつもりでも、相手に届いていなければ意味がありません。
伝言メモをデジタルで効率化する方法
デジタルメモアプリの活用例
最近では、手書きだけでなく、スマホやパソコンで伝言メモを作成・管理する人も増えています。無料で使えるメモアプリ(Google Keep、Evernote、Notionなど)を使えば、伝言内容を即座に記録でき、後から検索や整理も可能です。
紙よりも早く、共有も簡単なので、特にリモートワークが増えている今の時代には非常に便利です。
社内チャットと連携して残す方法
SlackやChatwork、Teamsなどの社内チャットツールを使って、伝言メモをそのまま共有する方法も効果的です。テンプレートを決めておけば、誰が見ても分かりやすく、記録も自動的に残ります。
たとえば次のようなフォーマットを使うとよいでしょう:
【伝言メモ】
■宛先:営業部 佐藤さん
■差出人:株式会社ABC 鈴木様(03-xxxx-xxxx)
■日時:10月14日 14:30
■内容:資料について折り返し希望とのこと
■対応:14:35 メモ渡し済(山田)
誰でも同じ形式で書くことで、情報のばらつきを防げます。
スマホでメモを写真に撮って共有
手書きメモを写真に撮って、LINEやチャットで共有するという方法もあります。急いでいるときや、書く時間がないときにはこの方法が役立ちます。
ただし、手書きの内容が読みにくいと逆効果になるため、できるだけきれいに書き、写真もはっきり撮るようにしましょう。
テンプレートをクラウド保存して使いまわす
毎回ゼロから書くのではなく、あらかじめテンプレートを作っておき、GoogleドライブやDropboxなどのクラウドに保存しておくと効率的です。必要な時にコピーして、内容だけを変更すればすぐに使えます。
チーム全体で共有しておけば、誰が対応しても同じ品質で伝言メモが作れるのもメリットです。
紙とデジタルの併用で「ミスゼロ」へ
最も理想的なのは、紙とデジタルの併用です。手書きで素早くメモを取り、あとでデジタルで記録を残すことで、どちらかが紛失しても安心です。また、紙で渡しながら、チャットで「伝言メモを渡しました」と通知することで、伝達ミスを限りなくゼロにできます。
業務の効率化だけでなく、情報共有の正確さを高めるためにも、両方の手段を上手に活用していきましょう。
まとめ
伝言メモは、シンプルながらもビジネスマナーや信頼構築に欠かせない重要なツールです。正確な情報を丁寧に、分かりやすく伝えることが、「できる人」としての印象をつくります。
紙でもデジタルでも共通して大切なのは、相手の立場に立って、わかりやすく伝えること。今回ご紹介したテンプレートやルールを活用すれば、誰でも今日からすぐに実践できます。
小さなメモ1つで、あなたの仕事の信頼度がグッとアップするかもしれませんよ。
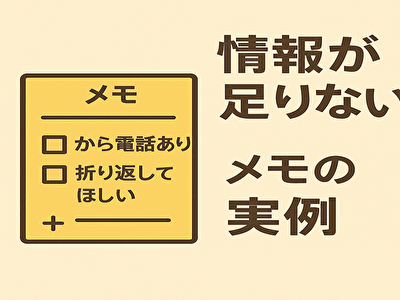
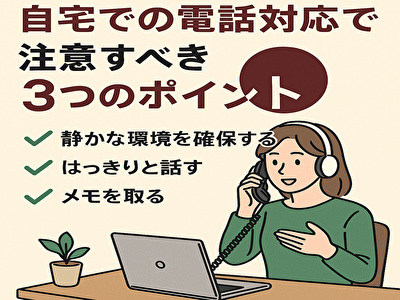
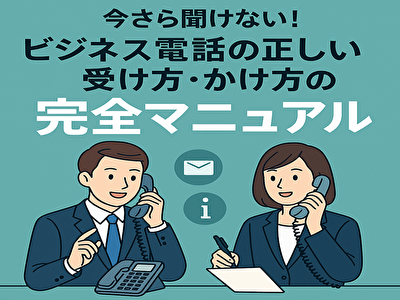
コメント Comments
コメント一覧
コメントはありません。
トラックバックURL
https://adpurasu.net/11.html/trackback